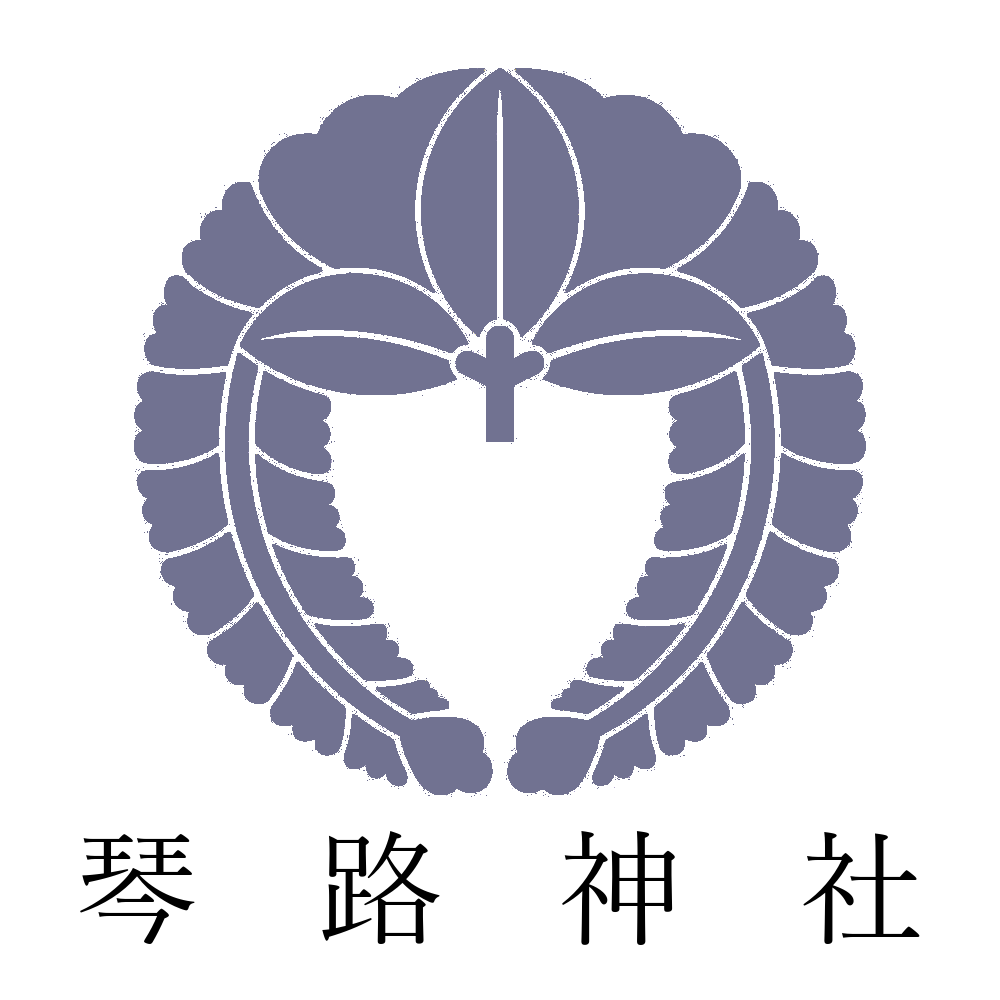境内が伝えてくれることPrecincts
|
当神社の由緒や歴史は、過去の文献等に多数示されております。 しかしながら、それが全てというわけではありません。 現在、境内に残されているものでも、何故そこにあるのか、どういう意味があるのか不明な物もあったりします。 そうしたものを取り上げて、わかる範囲でお知らせしたいと思います。 先ずは10項目程を目標に、今後不定期ではありますが、様々な事を取り上げていきたいと思っております。 お参りの際には、どうぞご参照下さい。 以下に続きます。 |
|
境内には、手水鉢(手水石)が3口ありますがその中で一番古いと思われるものの縁には、何やら窪み状の穴が多数確認できます。 窪みは大小・深浅様々です。はたして、これは一体何なのでしょうか? 以前(令和元年)、当神社にお参り頂いた方がご自身の「旅人のブログ」の中で(https://tabi-bito.net/kinro-shrine-kashima-city-saga-prefecture/)、この窪みに ついての御指摘がありましたが、これは「盃状穴」というもののようです。 調べてみますと、「歴史は先史時代(日本における縄文時代頃)にさかのぼる」とか、「世界中にその存在が認められる」等大変な代物らしいのですが、果たしてその意味については様々な見解があるようです。 件の手水鉢は江戸期に奉納された物のようですが、経年劣化が著しく文字の判読も難しい為、年代の特定には至っておりません。国内における説明では、繁栄・再生・不滅等を願う信仰の対象であるとされているようです。境内では、この手水鉢だけでなく、他の場所でも確認できますのでお 参りの際には、是非探してみて下さい。 全国では文化財に指定されているものも多数あるようですが、県内にある盃状穴について調査・研究するのも面白いかもしれません。 |
|
みなさん、「バクチの木」と呼ばれる樹木をご存じでしょうか? 樹皮は灰色だったり黄みを帯びた色ですが、やがて少しづつ割れてはがれ落ちてきます。 その下にはレンガ色のような幹が現れますが、これを通年にわたり繰り返しているようです。その様子は、まるで「博打(ばくち)に負けて、身ぐるみはがされた様子に似ているから」ということからきているそうです。 例年、境内のバクチの木は9月中旬頃に花をつけますが、気がつかない方がほとんどです。 しかし昨年は、10月半ばまで迄気温が高く開花時期もずれてしまい、10月末の神幸祭・例大祭準備の頃に満開となり御奉仕に集まった皆さんがしきりに写真を撮られておりました。その後急激に気温が下がった為に、まるで冷蔵庫に保存された様に半月過ぎた頃でも花が咲いている状態でした。 現在、境内には4本ほど自生していますが、以前行われた佐賀県の調査ではそのうちの1本が樹齢320年以上という報告もありました。ちなみに剥がれた樹皮は、「賭け事のお守りになる」という方もいるそうですが、皆さんお試しになりますか? 

|
|
鎮守の森には、多種多様の植物が自生しています。当神社の境内にも樹木・草花・苔類等々、一体どれくらいの種類になるのか見当も付きません。そこで普通に考え、区別がつきやすいのは樹木ではないかと思います。 地理的にも照葉樹類の育ちやすい地域で、クスは佐賀県の木にもなっております。 さて、皆さんはこの木のことをご存じでしょうか? 「クサフ」+「ノ」+「イゲ」 → 「ハリネズミ」+「ノ」+「トゲ」 「クサフ」・・・ハリネズミの古い呼び名。また、草の生えている場所→その様子・状態を意味するのか? 「ノ」・・・・・助詞。前後の言葉の関係をしめす。 「イゲ」・・・・九州方面の方言。するどい「トゲ」を「イゲ」と言う。 鋭いトゲに加えて、幹の樹皮がハリネズミの背中を連想させるのでしょうか?ちょっと変わった珍しい木だと思っていましたが、近畿地方より西・南の地域の海岸近くの林で見られるそうす。 
|
|
この「クスドイゲ」という木ですが、実は長い間正式名を知りませんでした。今は、スマートホン・アプリで画像検索ができるそうですが、数年前まではそのような便利なものがありませんでした。 この「クスドイゲ」という木の存在に初めて触れたのは、かれこれ40年ほど前になります。当時、奉職先の神社にいらっしゃった女性職員の方に教えて頂いたときには、「ヨロイノキ」と呼ばれていました。幹の樹皮の様子で、「まるでこの木が鎧(よろい)を身に付けている」様だという説明でした。正式な名称ではないだろうと思いつつ年を重ねる中で、まさか境内にも自生しているとは思いもしませんでした。 さて、平成20年代の半ば頃、朝日テクノ㈱(本社・佐賀市)の職員2名の方が当地区の樹種・植生調査にて境内にいらっしゃいました。御挨拶をかねて声を掛け、立ち話の流れで「この木の名前とか解りませんかねぇ?」と言う事になりました。すぐには解らないので枝葉を採取して帰り、改めてご回答頂く事になりました。少々時間がかかったかと思いますが、「クスドイゲ」という正式名を教えて頂いたという経緯があります。 この木について調べてみると、面白い特徴があります。銀杏などもそうですがこの木には雌雄異株といって、オスの木とメスの木がある様です。花が咲くと見分けやすいそうなのですが、雄花(おばな)は雌花(めばな)よりも大きく、沢山付くのでよく目立つようです。また、現在でも節分の日になると,「厄除け」「鬼払い」としてタラノキの枝にイワシの頭を挿す習慣が残っているところもありますが,瀬戸内の島のなかには,タラノキの代わりにこのクスドイゲの枝にイワシの頭を挿すこともあるという事です。 
|