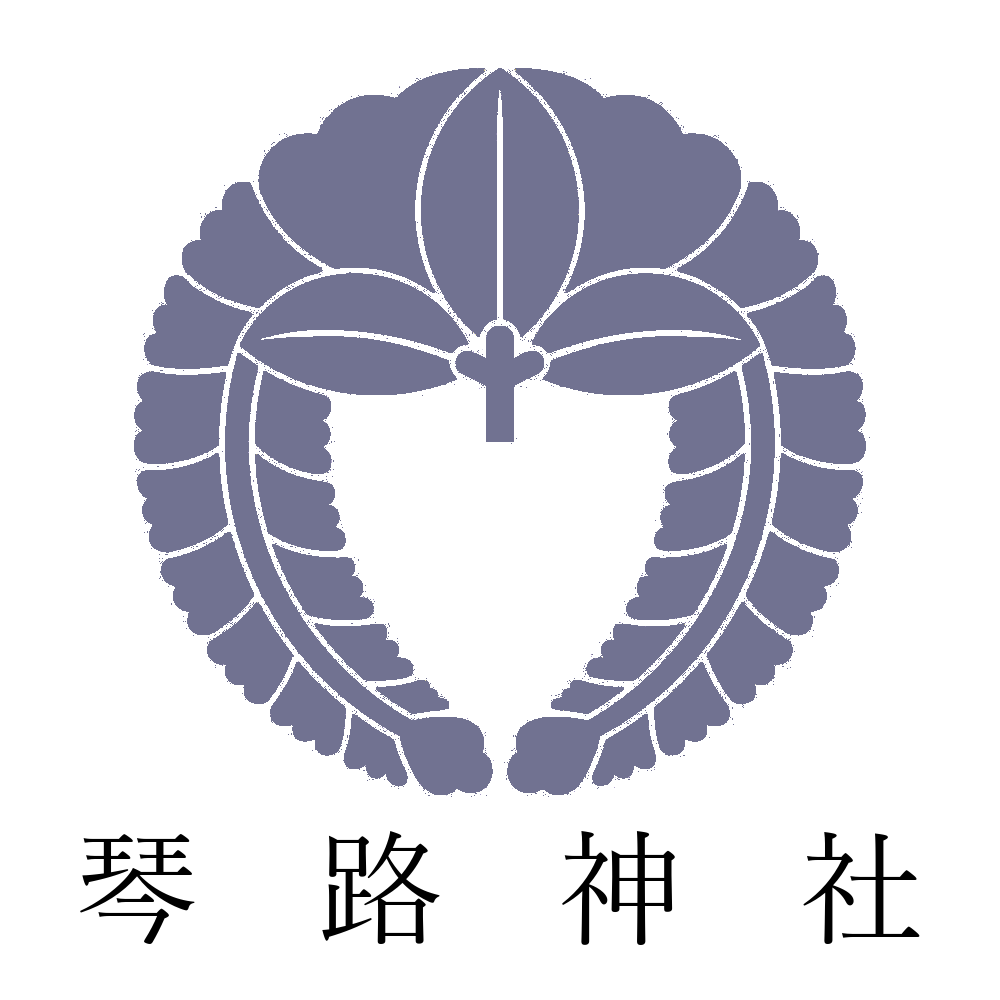御由緒・祭事History and festivals
|
【神社名】 【鎮座地】 【御祭神】 【琴路神社御由緒】 |
|
当神社の由緒や歴史は、過去の文献等に多数示されております。 しかしながら、それが全てというわけではありません。 現在、境内に残されているものでも、何故そこにあるのか、どういう意味があるのか不明な物もあったりします。 そうしたものを取り上げて、わかる範囲でお知らせしたいと思います。 先ずは10項目程を目標に、今後不定期ではありますが、様々な事を取り上げていきたいと思っております。 お参りの際には、どうぞご参照下さい。 境内が伝えてくれること |
|
1月 1日 歳 旦 祭 |
|
当神社は佐賀県鹿島市にあり、藤津郡にあった旧鹿島町を中心に能古見と古枝の一部で構成される地域の守り神として、氏子の皆様より御崇敬を頂いております。 令和2年には御創建と伝えられる鎌倉期の仁治2年(西暦1241年)より780年の節目の年を迎えました。 此の慶節に合わせ、平成27年度には御鎮座780年臨時大祭の斎行と記念事業の計画が立てられました。内容については予てよりの懸案であった、再興から約190年を経て老朽化が深刻となった御神輿2基の改修事業と御神輿庫の新設を柱として進められてまいりました。 予定した事業も整いつつありましたが、当年春より拡大した新型感染症の影響で10月17日に予定しておりました臨時大祭は11月の例大祭に併せての斎行となり、一連の行事は規模縮小・自粛を余儀なくされる事態となりました。 そうした中でも6年間に亘る氏子地区からの奉賛に加え、趣旨御賛同を頂いた多くの方々のお力添え、行政による文化財保護助成事業の活用等で当初予定していた記念事業につきましては無事完了する事が出来ました。これも偏に、皆様方の真心が御祭神の御心に叶った験であると確信致しております。 この度の記念事業の詳細につきましては境内の記念碑に刻し、御奉賛頂きました方々の末永き顕彰を申し上げたいと存じます。
【御鎮座780年臨時大祭】
【御鎮座780年記念事業】 |
琴路神社神幸祭行事(平成30年10月30日 佐賀県重要無形民俗文化財の指定)
神幸祭


神幸祭とは1年に1度、神社の御祭神に御神輿(おみこし)にお遷り頂き地域の発展や、現在の氏子の人達の暮らし向きがどの様であるかを御覧頂くと共に、 普段神社にお参り出来ない方々にも神様への感謝を込めてお参り頂き、更なる御加護戴く神事で毎年11月2、3日の両日行われます。
初日は新宮神社(しんみやじんじゃ)へのおくだりが行われます。琴路神社で神輿を出発させる発輿祭(はつよさい)を執り行ったのち、神幸行列が始まります。 行列の露払いを「獅子」と「剣突き」が務め、桶に塩水を入れ榊で払う「神水振」(しめふり)、割れ竹で地面を打ちながら進む「先祓」(さきばらえ)を先頭に出発し、御神輿、威儀物・道具持ち、提灯持ち、お供の浮立(ふりゅう)がこれに続きます。 途中、琴路宮(ことじぐう)にて仮宮祭を執り行い、夜間に新宮神社(しんみやじんじゃ)に到着し、着輿祭(ちゃくよさい)の後同神社境内にて一晩お鎮まりになられます。
二日目は昼過ぎに新宮神社で発輿祭(はつよさい)を執り行いおのぼりが行われますが、初日とは別のルートを進みます。 夕刻、琴路神社に到着し、馬かけ神事後に神輿を神殿に納め、例大祭斎行ののち、直会をもって締めくくりとなります。 参加者は両日とも三百名以上に及び、県内の他の神幸行列と比較しても規模が大きい事も特徴です。
神幸祭の様子は、下記アドレスよりご覧いただけます。(平成29年11月2・3日斎行画像)
https://saga-kashima-kankou.com/feature/4396
令和3年 神幸祭予定表(PDFファイル) 渡御・お上り順路/渡御・お下り順路
獅子と剣突き


獅子は赤と青(緑)の2頭で、各々2名が舞い手となります。赤獅子が雄、青獅子が雌とされています。 渦巻模様があしらわれた布を獅子頭につけ、法被、股引き姿に白足袋、草靫を履いた姿で演舞を行います。 獅子の頭は正面から見ると丸型、横から見ると扁平状でありその形から獅子面とよばれ、目はアーモンド形でユーモラスな表情をしています。
剣突きは獅子に付随し、「猿田彦」とよぶ赤天狗、「烏天狗」とよぶ青天狗の二名が舞い手となり、赤青の天狗装束をつけ、手甲、脚絆に白足袋、草靴を履き、金属製の刃がついた木製棒状の鉾をもちます。獅子の舞が終わると、その動作に合わせて「オー」という掛け声を発し、双方から互いに歩み寄り、鉾の刃を上下の位置で合わせたり、相手の柄部分を打ったりして演舞を行います。
馬駈神事


馬かけ神事は、お上り終盤に行われます。神社の『御神馬名簿』によれば、昭和初期には30頭以上の地元の農耕馬が神事に参加していましたが、平成の御代に入る頃から農作業の機械化が進み市内から参加する馬はなくなり、他県の牧場より数頭を用立てしています。
御神輿行列が鳥居前に差し掛かると、人を乗せた馬が御神輿の後につきます。やがて馬が先を争って境内に入ろうとしますが、台車から降ろされた御神輿は馬を入れまいと鳥居や神橋で横向きとなりそれを遮ります。この掛け合いが何度も繰り返されながら境内の奥へと移動したのち、先に御神輿が鳥居をくぐりその後に馬が続きます。境内へとなだれ込んだ馬は、我先にと社殿を数周時計回りに駆け回って終了となります。
民俗芸能
氏子内の民族芸能について
氏子26区の中には、様々な民俗芸能が伝えられ保存されています。浮立と呼ばれる芸能や獅子舞・剣突等神社の祭礼時に奉納されたり、それぞれの地区の行事等で演奏・演舞され今日に至っております。 曾ては地区内の青年達が中心となり行われていましたが、現在では社会の多様化や地域住民の高齢化等で子供から高齢の方まで地域をあげて伝承と保存に務められています。
鹿島市内の芸能等についての詳細は、下記アドレスよりご覧下さい。(鹿島市HP[PDFファイル])
https://www.city.saga-kashima.lg.jp/html/site_files/file/toshikeikaku/2-4furyuu.pdf
山浦面浮立(やまうらめんぶりゅう)


面浮立は佐賀県を代表する民俗芸能で、鬼の面をつけた「かけうち」が、笛や太鼓の音と共に踊ります。
鬼の面をつけて勇壮に踊る姿は珍しく特に鹿島市には多く残っています。